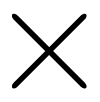ブログ
骨粗しょう症について サプリは有効?
こんにちは
今回は「骨」についてのお話です。
トレーニングサロンで骨の話?と思われるかもしれません。でも骨と筋肉は超密接な関係。
骨が弱くなると筋肉も弱くなります。
筋肉は骨から骨につながっています。その支えとなる骨が弱ければ筋肉に引っ張られてポキッとはならなずともリスクは高まります。つまり、筋肉をしっかり働かせるためには強い骨が必要です。
骨密度低下=骨粗しょう症なの?
いいえ。骨粗しょう症は「骨の強さ(骨強度)が低下した」状態です。骨強度は骨の「量」と「質」で判断します。この「量」を計測するのが「骨密度検査」です。「質」はCT、尿検査、血液検査などで判断します。
それらが規定値より下回った時「骨粗しょう症」と診断されます。
原因は?
・女性ホルモンの低下
・飲酒
・喫煙
・運動不足
・低体重 など
閉経と骨粗しょう症の関連はよく耳にする話ですね。ほかの項目もすでにご存知の方も多いと思います。
対策は?
さて、ここから今回の本題です。サプリメントは有効なのでしょうか。
結論から申し上げますと、「微妙・・・」です。
カルシウム
閉経後の女性が牛乳を中心とした乳製品を摂取した結果、骨密度の増加を認めたという報告があります。普段のカルシウム摂取が少ない方で顕著だったそうです。
同じように50歳以上の女性を対象とした研究でも、年単位の継続で骨密度が改善したと報告されています。
忘れてはいけないのは、加齢とともに骨密度は低下するということ。閉経後、ガクっと下がった骨密度は一定ではなくその後も徐々に低下していきます。骨密度の低下と同じ、またはそれ以上の改善をめざさないと骨密度は上がらない ということです。
サプリメントは有効?
食事であがるならサプリを摂ればもっと上がりそう!なんて思いますよね。
でも体は体内のカルシウムバランスを保とうとします。たくさん摂ったからといってすべてが栄養になるわけではありません。
食事+サプリメントで骨密度が上昇した という報告ももちろんあります。でもその効果は「わずか」というものが多いのも事実です。つまり摂取はOKだけど効果は期待小かも という見解です。
基本は食事から。牛乳やチーズなどの乳製品を1日700~800mg摂取します。
実際どのくらいかというと
約200mg摂取するために
牛乳 カップ1杯(200ml)
小松菜 1/2束
木綿豆腐 2/3丁
ひじき 大さじ3以上 をそれぞれ摂取すると800mgです。
それなりの量ですが、この中から3種類を選んで1日の中で分けて摂取しようと思えば無理なほどではないのかもしれませんね。
だからこそ、サプリメントの効果は「わずか」となってしまうのだと思います。
ビタミンD
よく耳にしますが、どんな役割があるかというと・・?ですよね。
・カルシウムの吸収を良くする
・骨を強くする(石灰化を促進する)
ビタミンDを含む食材は、さんま、鮭、ぶり、しいたけ、きくらげなどです。 それぞれ普通の1人前の量で賄えるので、魚食を意識していれば十分そうですね。
そして食事と同様に大切なことは「太陽をあびること」です。皮膚で紫外線をあびることで体内で産生されます。
日差しの強い地域とそうでない地域でビタミンD産生量にも差が出ると言われています。日焼けはしたくないけれど骨密度は保ちたいですね!女性としては判断が難しいですね・・・。
サプリメントについては、大腿骨頸部(骨折しやすいところ)の骨密度の変化率が上がったという報告があるようですが、他の部位(大腿骨近位部や腰椎)では変化がなかったそうです。他にも「改善した」という類の報告がありますが変化率は少ないようです。つまり、飲んだら効果がありそうだけど、なんとも言えないという感じでしょうか・・・。
肥満と痩せは関係ある?
さて、一番気になるところのお話です。
肥満度を表す【BMI】はご存知ですか。健康診断の身長体重の次くらいに書いてあることが多いです。単位はkg/m2ですが今回は省略して書きます。
標準値は18.5~25です。50代60代だと21~25くらいが目安です。25以上は肥満と判断されます。
このBMIと骨密度、実は関連があります。18.5以下の「痩せ」の方は骨粗しょう症の診断率が高くなります。一方、25以上の女性は骨粗しょう症の頻度が少ないです。骨折リスクも似たような結果です。
どうやら体重が少ないということは、栄養状態も少ないということが原因のようです。しっかり栄養を取って体重を維持することで骨量がたもたれます。
でも!肥満がいいというわけではありません!生活習慣病を引き起こす可能性が高くなりますので、適正体重を保ってくださいね!
まとめると「栄養は食事から、体重は適正に」が私の結論です。
今回は、厚生労働省の指針をまとめてみました。詳しくは001316479.pdfで紹介されています。
運動についてはまた改めてお話します!
お読みいただき有難うございました。